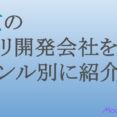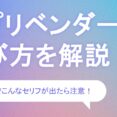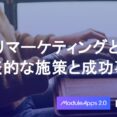販促や集客、ブランディング戦略を読み解く専門メディアモバイルマーケティング研究所
アプリ開発の流れと手順を6ステップで解説!期間や費用も
自社でアプリを作りたい! と思っているものの、
「アプリ開発って何から手をつければいいの?」
「要件定義って最初にやるんだっけ?」
「開発の全体像も、具体的な手順も、全く分からない」
……と悩んでいる方、多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、2010年からアプリ開発事業をおこなっている弊社の知見から、アプリ開発の企画からリリース、その後の運用までの基本的な流れや開発手法について詳しく解説します。
さらに、実際に開発会社へ相談するタイミングや、開発会社の選び方のポイントも解説していますので、アプリの導入を検討している方、少しでも興味がある方は、ぜひ最後までご覧ください!
アプリ開発の流れ・手順を6ステップで解説
1.企画立案
まずは、「アプリを活用して何を達成したいのか」「自社のどんな課題を解決したいのか」という目的をはっきりさせます。
そのうえで、
・アプリ事業にかけられる予算と期間
・実装したい機能(アプリ内でユーザーにどんな体験をしてもらうか)
・KPIの設定(ダウンロード数/アクティブユーザー数/会員数など)
といった部分を深掘りし、企画に落とし込みましょう。
【応用編】アプリ開発の型
予算と期間について検討する際、アプリの「開発の型」を理解しておくとスムーズです。
アプリ開発には大きく3つの型があり、どの型を選ぶかによって「アプリに実装できる機能・デザインの幅広さ」「かかる費用や期間の目安」などが大きく変わってきます。それぞれの特徴を押さえておきましょう。
①低予算・短期間重視なら「ノーコード型」
・数万円〜アプリ制作が可能。
・カスタマイズ性や連携機能が低いため、やりたいことが実現できない場合も。
②完全オリジナル重視なら「フルスクラッチ型」
・実装できる機能やデザインの幅が広く、自社オリジナルのアプリを作ることができる。
・1000万円以上~と費用も高く、制作期間も長め。
③機能・デザインのバランス重視なら「ハイブリッド型」
・フルスクラッチ型とノーコード型の中間
・価格を抑えながらも、独自の機能を実装することができる。

NTTドコモ子会社のアプリ開発会社 DearOneが提供する「ModuleApps2.0」は、ハイブリッド型開発を採用しており、低価格で独自性のあるアプリ開発が可能です。
また、事前準備のコツとして、累計1億DL以上のアプリを支援してきた弊社の知見から作成した資料もございます。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
>「アプリ開発で失敗しないために、最初に知っておくべき4つの視点」資料DLはこちら
2.要件定義
要件定義は、企画で決めた内容を軸に「アプリに求めること」を細部まで詰め、システム要件へと変換する作業です。
アプリに必要な機能はもちろん、ページの読み込み速度やセキュリティといった非機能要件についても言語化し、開発側と発注側での認識をそろえることが大切です。
要件定義が曖昧だと、途中で仕様変更が必要になったり、予算がオーバーしてしまったりと計画が崩れる原因になりますので、この工程は非常に重要です。
何から手をつければいいか分からない場合でも、経験豊富な開発会社であれば、ヒアリングを通じて必要な要件を一緒に整理してくれます。後の失敗を防ぐためにも、プロの知見を得ながら要件定義を行うことは有効ですので、迷いがあるという方もお気軽にお問い合わせください。
💡関連記事:アプリ要件定義の完全ガイド【チェックリスト付き】
3.設計・開発
設計は、「外部設計」「内部設計」の2種類に分けられます。
外部設計では主に、操作方法やデザインなど、“ユーザーの目に見える部分”の設計を行います。
一方内部設計は、データベースやインフラなど、システム周りの設計を指します。
ここでアプリ内外の仕様が固まったら、あとはエンジニアが設計通りにプログラミングを行うことで開発が完了します。
外部に開発を依頼する場合は進捗が見えづらい部分ですが、定期的にコミュニケーションをとり、状況を確認することが大切です。
【応用編】アプリ開発手法の種類
ここで、アプリ開発における代表的な2つの手法について解説します。
開発手法によって、細かい流れや注視すべきポイントが異なりますので、目的や案件規模によって最適な手法を選ぶことをおすすめします。
ウォーターフォール開発
ウォーターフォール開発は、要件定義→設計→開発→テスト→リリース……と、基本の開発工程を上から順番に進めていく手法です。
すべての工程において、「企画/要件定義」で定めたゴールに基づいて動くので、初めからアプリの要件や仕様について細かく決めておく必要があります。
メリット
●狙い通りの開発を行うことができる
●スケジュール・進捗管理がしやすい
●必要な人員の目安、予算などの見通しが立てやすい
→各工程にしっかり時間を取り、決められた順番に沿って1つ1つ着実に進めていくため、要件で定めた希望通りの開発を行うことができます。
また、取り掛かるべき順序やタスクが明確で、開発の進捗状況を把握しやすいというメリットもあります。
デメリット
●リリースまでに時間がかかる
●途中で計画変更・方向転換するのが難しい
→途中で仕様変更やトラブルが発生すると、再び上流工程に戻り、要件から設定し直す必要があります。そうなってしまうと、スケジュールの見直しも含めて大幅な工数がかかります。
ウォーターフォール開発が適しているケース
・複雑で、緻密さが求められる開発
・大規模で全体スケジュールの管理が必要な開発
・初期段階から企画のゴールが明確で、変更の可能性がない案件
アジャイル開発
アジャイル開発では、大まかな企画・計画が決まったら、設計→開発→テスト→リリースという小さなサイクルを繰り返します。
各工程ごとに丁寧に進めるウォーターフォールに対し、リリースまでの期間が短く、リリース後もユーザーの反応を見ながら機能の追加や改善を繰り返すことが前提とされています。
メリット
●仕様変更やトラブルに対して柔軟に対応できる
●短期間で開発を終えることができる
●ユーザーの反応を元に改善を繰り返すことで、世の中のニーズにこたえやすい
→特にDX化が進む中では、世の中のニーズが変化しやすく、また想定外のトラブルなども起こりやすいため、近年注目されている手法です。
デメリット
●スケジュールや方向性がブレやすい
●予算の見通しが立てにくい
→ウォーターフォールのように綿密な計画は立てず、最終形態が不透明なまま開発が進みます。そのため、方向性や全体スケジュールが見えにくく、予算の見通しも立てづらいというデメリットがあります。
アジャイル開発が適しているケース
・細かい進捗管理が不要な小規模開発
・短期間での開発が求められる案件
・開発途中での仕様変更が想定される場合
「ModuleApps2.0」ではウォーターフォール開発を採用していますが、各機能のモジュール(テンプレート)があるため、一部の開発とテスト工程が少なくて済むことが特徴です。
そのため、通常のウォーターフォール開発よりも短期間で、柔軟性の高い開発が可能です。さらに、リリース後の伴走支援も整っており、ユーザーの行動分析・改善も柔軟に行うことができます。
4.テスト
開発が完了したら、設計通りに操作できるか、などを確認するテストに移行します。
軽視されがちな工程ですが、リリース後のエラーやバグを防ぐための大事な工程です。
セキュリティ、外部システムとの連携、ページ遷移・読み込みの速度、操作のしやすさや画面表示に問題がないかなど、様々な角度からテストが行われます。
開発側だけに頼らず、発注者側でも実際に操作し、「設計通りの機能が実装されているか」「操作感に問題はないか」といった観点でチェックしましょう。
5.申請・リリース
テストで問題なくアプリが使えることが確認できたら、いよいよ公開に向けて動きます。
アプリをリリースする際には、App StoreやGoogle Playへの申請が必要で、通常は開発会社が代行します。
ただし、申請に必要なアプリの説明文や画像素材などは、発注者側で用意する必要があります。
審査結果が出るまでの期間も考慮し、リリースのスケジュールは余裕をもって組みましょう。
各ストアの審査を通過すれば、ついにアプリが公開されます!
6.運用・保守
アプリ公開後も、エラーやバグが発生していないか監視する必要があり、不具合が発生した場合は迅速な対応が求められます。
こういった「運用・保守対応」は通常、開発会社がサポートサービスとして提供しています。契約前に、サポート体制や追加費用の有無などを確認しておくと安心です。
アプリはリリースしてからの方が大切なので、開発会社に依頼する場合は「長期的なパートナーとして信頼できるサポート体制があるか」という視点でも見てみましょう。
開発会社に相談する際のポイント
ここまで、アプリ開発の流れについて解説してきましたが、「どの段階で開発会社に依頼・相談すればいいの?」と思った方もいるかもしれません。
結論、「早ければ早いほどいい」です。
早めに相談することで、費用・期間・制作可能なアプリのイメージがより具体化されます。
経験豊富な会社であれば要件定義のアドバイスなどもしてくれますので、「要件が固まっていない」「社内合意が取れていない」という場合でも、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。
とはいえ、早すぎる相談は躊躇してしまう方も多いと思いますので、【相談前】に整理すべきポイント、【相談時/後】の開発会社の選び方、についても解説していきます。
相談前に整理すべきこと
アプリ導入の目的
「なぜアプリを導入したいのか」という目的を明確にすることは必須です。
目的が定まっていないと、開発会社側も正確な見積もりを出すのが難しく、問い合わせ後も話が進みづらくなってしまいます。
逆に目的が明確であれば、「〇〇達成のためにはこの機能がおすすめ」「過去の実績でこういったものがある」といった形で、機能や予算感の相談に広げていくことが可能です。
希望予算・スケジュール感
・いくらまで予算をかけられるか
・リリース希望時期はあるか
の2点も、事前に社内で確認を取っておくとスムーズです。
予算と期間は、最初にお伝えした「開発の型」に大きく左右され、開発会社によってどの型を採用しているかは異なります。
そのため、「絶対この予算内に/この期限内に収めたい」という明確なラインがある場合、相談する開発会社を絞り込みやすくなります。
どんな機能を実装したいか
目的を達成するために、どんな機能を入れるべきかも具体的に考えておくとベストです。
①絶対に入れたい(最低限ほしい機能)
②できれば入れたい(目標達成にブーストをかけてくれそう)
③あったら便利だけど、様子を見て検討したい
といった形で優先順位をつけておくと、「予算と機能、どこでバランスをとるか」の判断材料にしやすくなります。
開発会社選びで失敗しないために
自社の目的と近い実績をもつ会社を探す
アプリにもさまざまな種類があるように、開発会社によって得意なジャンル・強みは異なります。
開発会社のHPで過去の導入実績を確認し、自社の業界や事業、取り入れたい機能など、目指すゴールと近い実績を持つ会社を選びましょう。
また、アプリ開発は非公開実績も多いため、相談時に「こんな事例があったら教えてほしい」とヒアリングしてみるのもおすすめです。
弊社にも多くの非公開実績がございますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
複数の会社から見積もりを取る
ある程度候補先を絞れたら、複数の会社に見積もりを依頼しましょう。
複数社を比べることで、「機能の充実度に対する価格差」「テストや運用・保守の範囲といった対応の充実度」などがより具体的に見えてきます。
また、担当者とのやり取りの中で「コミュニケーションがスムーズにとれるか」も確認してください。
アプリをリリースしている限り、開発会社との付き合いは長期的に続きます。やり取りの中で違和感や不信感がないか、も大事なポイントです。
リリース後の運用まで見越した計画を立てる
リリース後は、基本的な運用・保守体制はもちろんのこと、「目標に対して成果が出ているか」も追う必要があります。
想定していた効果が出ていない場合に、「機能を追加すべきか」「キャンペーンを行うべきか」など、施策やアップデートの面でサポートしてくれる体制が整っていると、より安心して依頼することができるでしょう。
💡関連記事:アプリ開発会社のおすすめ12社をプロがジャンル別に紹介
まとめ
アプリ開発における一般的な流れや全体像をお伝えしてきましたが、目的によって採用すべき「開発の型」「開発手法」は異なります。
まずは導入の目的を整理し、自社にあった開発会社を選ぶことがアプリ開発成功の近道です。
NTTドコモ子会社のDearOneによる「ModuleApps 2.0(モジュールアップス)」は、豊富な機能の中から必要なものだけを選択して組み込むことで、低価格で独自性のあるアプリ開発が可能です。
ハイブリッド型開発を採用しており、アプリに関する幅広いお悩み・ご要望にも柔軟に対応することが可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください!