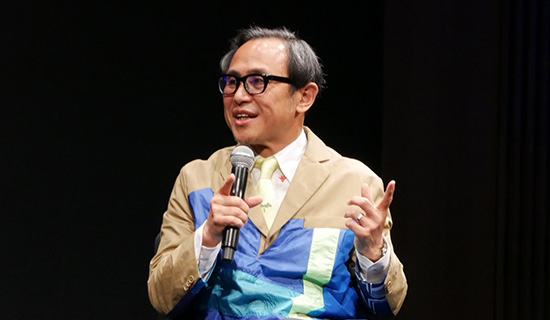販促や集客、ブランディング戦略を読み解く専門メディアモバイルマーケティング研究所
「自らのストーリーで顧客を動かす」放送作家 鈴木おさむ氏、スマイルズの遠山正道氏が語る顧客体験の価値
食べるスープの専門「Soup Stock Tokyo」などを展開するスマイルズ社長の遠山正道氏と、多くのメディアで活躍する放送作家の鈴木おさむ氏との対談。スープ専門店を企画する立場や、ヒットする番組を企画する立場から、顧客体験とは何かについて語った。


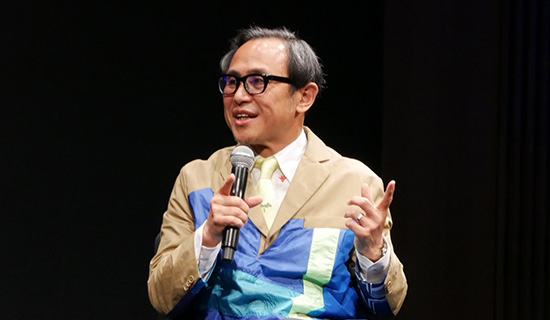

(画像左より)放送作家 鈴木 おさむ氏 /株式会社スマイルズ 代表取締役社長 遠山 正道氏
4月17日、CXプラットフォーム「KARTE」を運営するプレイドが主催する「CX DIVE 2019」で、放送作家の鈴木おさむ氏とスマイルズの遠山正道氏より「変わる世界、うねりとしてのCX」というテーマの対談が行われた。
目次
開く
スープ専門店が始まったきっかけ
鈴木:世の中でヒットするものって、ありそうだけどないものだと思っています。それは全くないものより、これ何でなかったのだろうというものが結構ヒットしているなと思っていて、でもそこを見つけるのが難しいのですが、スープ専門店も今までなかったですよね。 遠山:個人的な考えかもしれませんが、ヒットさせようという感じはありませんでした。当時私は商社に勤めるサラリーマンでした。とあるきっかけによって個展をやり、それがきっかけで、自ら何かを生み出して、世の中に提案することをやりたいという想いが強くなりました。 食やリテールなど手触り感のある仕事をしてみたいという想いもあり、商社の関連会社に日本ケンタッキー・フライド・チキンがありましたので、そこに出向させてもらいました。何か新しいものがやりたいなと考えていたある時 女性がスープを飲んでホッとしているシーンが浮かんできて、何か大事なものと出会えた気がしました。そこから3か月かけて、物語形式の企画書を書きました。企画書を物語にした効果
鈴木:その企画書を物語にしたのはなぜですか? 遠山:1990年代まで話は戻るのですが、 情報産業グループに異動し、初めてパソコンを使いました。電子メールやパソコン通信を使っているうちに、これはすごいと世の中が変わるような衝撃を受けました。当時は商社でもまだパソコンが普及していなかったものですから、上層部にパソコンの導入を勧める企画書を書いたんです。 電子メールがビジネスで活躍するストーリーをまとめた「電子メールのある1日」という企画書を書きました。その企画書は最終的に三菱商事の社長まで上がっていって、私の成功体験になりました。その時に物語はイメージを共有しやすいと思ったのです。 仕事は1人ではできないので、共感する仲間を集めなければいけない。自分が思い描いているものを共有し、共感してもらうためにどうすればいいかと思った時、以前の成功体験から「スープのある1日」という物語形式の企画書を作りました。 鈴木:たまに能書きがたくさん書かれたプレゼン資料があるのですが、「なぜこの企画をやるのか」という説明が4~5枚も書かれていると、僕は結構見ていられなくて、ああいうのは才能ある人ほど飛ばすじゃないですか。 めちゃイケの前身で「めちゃx2モテたいッ!」という番組があって、出演メンバーが毎週モテるために挑戦する番組があったんです。その企画書の1ページ目に、「あなたは何で髪の毛をセットしてきましたか? あなたは何でその色のネクタイをしてきましたか? あなたは何でそのスーツを着てきましたか? それはモテたいからです」と書かれていたんです。 なんだかその企画書を読んだ時、「他人事」から急に「自分事」に変わって、それですごくいい企画書だなとずっと思っていて。企画書をもらうと読むのが面倒くさかったりするけれど、それが物語となると気持ちが没入するので、「自分事」にさせているのかなと思っています。 遠山:その企画書には共感ということが書かれています。スープというものに共感して集まってくれた仲間が、作品のように商品を作って世の中に提案し、お客様や世の中と共感する関係性ができれば、やがて次の商品やサービス、物販に広がっていくだろうと思います。共感を得るための企画書だから、数字がメインにはなりません。 鈴木:世の中の共感で面白いのは、最近インスタで公開した写真がバズってネットニュースになったのですが、それは僕がコンビニの袋を首からぶら下げて、うちの妻である森三中の大島が僕の髪を切っている写真なんです。 バズったポイントは3つあって、1つは僕がコンビニ袋を付けていること、2つ目は洗濯物をたたまずに置いてあったこと、3つ目はうちの息子が来ているシャツがユニクロだったこと。そこの3つに対してやたらリアクションが多くて、フォロワーが何かを見て、自分で勝手に物語を作り出すのですが、なんだか共感させることってすごく強いですね。 遠山:そういう意味だと、写真を見た人が自分の物語を語り出すような、そういうきっかけや余白というものが、共感を生み出す1つのコツかも知れませんね。
マーケティングは使わない
鈴木:話は変わりますが、遠山社長はスープや、ネクタイや、海苔弁当など、広い業界よりも狭い業界を自分の中で狙っているのですか? 遠山:狙ってはいないのですが、専門店好きみたいですね。 鈴木:狭い業界を熱狂させるという感じではなくて、むしろその商品への想いが強いというわけですね。 遠山:うちの会社ってマーケティングがないと言っているのですが、例えばアーティストって来年個展をやる時、どんな絵を書いたらいいのかアンケートを取ることなんてしないですよね。自分のコンテクスト(コンセプト)を大事にして 自分が何かを感じ取ったら、それを世の中に提示する。そうすると いいねと言ってくれるお客様が現れる。だから世の中に提示することが礼儀みたいな気がしていますね。 鈴木:なるほどね。昨今のビジネスはマーケティングを大事にすることも多いですが、それに対してはいかがですか? 遠山:うちはないという感じですね。自分事と言っているのは、例えばビジネスって大変で、なぜやっているのか、どうしてやっているのかと立ち戻らざるを得ない場面がたくさん出てきます。その時「お客様がそう言っていたから」という、外に理由があると立ち戻れなくなります。だからメンバーの環境や生い立ちがビジネスの軸になっていないと、大変な時に踏ん張れず続けるのが難しくなります。 そういうことなので、うちはフランチャイズビジネスにも興味がありません。あとは、例えばデートの場合、どこに行こうかと言われて選ばれる店舗よりも、あそこのスープ最高だから行こうよと言われる店舗になりたいです。 マーケティングはないと極端に言っていますが、世の中のことって普通に暮らしていても分かるじゃないですか。例えば、うちでファミレスをやっていますが、それは自分たち自身が結婚し、子供が生まれて、スープストックトーキョーに入ろうとしてもベビーカーじゃ狭くて入りにくいから、ファミレスで横展開しようと、世の中にもそういう需要はあるのではないかと思います。自分たちのやりたいことをしたい
鈴木:サービスと売上との兼ね合いってあると思いますが、それはサービスのほうが勝っていますか? 遠山:そうですね。自分たちのやりたい場所に出店して、リスクはあるけど手を変え、品を変え、なんとか踏ん張りながら続けてきた歴史ですね。でも最初から、そこそこの場所で、そこそこの提案だと粘れないしうまく行かなかった時、虚しい気持ちになります。赤字で閉店する店舗があるのですが、やりすぎなくらい思い切りやったので良かったねという気持ちで閉店できます。自分たちで完結できるものがあれば、心に傷がないという感じです。 鈴木:それはありますね。僕も振り切った番組を作ったときは、中途半端に小細工しないで駄目なら終わろうみたいな、そういうことを言うリーダーが好きです。それを言ってくれるリーダーに惚れるというか、やめたあと何かが残るとしたら、きっとその人の人格なのだと思う。 遠山:そうですね。例えばアーティストが10枚の絵を描いて、7枚売れて3枚売れなかった時、その売れなかった3枚は失敗作と呼ばないですよね。毎回真心込めて10枚描いている。たまたま売れる商品もあれば売れなかったものもあるわけで、だからその限りにおいては痛みがないんです。 むしろ売れるはずの商品で、アンケートを取ったのに売れないと相手のせいにしてしまう。世の中のせいにしてしまうとすごく変なサイクルに入ってしまう。だから自分事でやりたいですよね。自分事でやれば全てが楽しめるし、失敗してもごめんなさいと言えます。